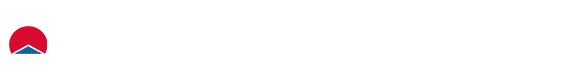保証金と敷金は、どのような違いがあるのか?
回答
保証金と敷金の違いとしては、実態としては、ほとんど同じような意味で使われていることが多いのですが、厳密に言えば、次のような違いがあるとされています。
1. 保証金は、事務所、店舗やテナントなどの主に法人契約によく使われ、敷金は、個人の住居の契約によく使われています。
2. 保証金は、約定によって、退去時に敷引き(解約引き、償却などと呼ぶ場合もあります)があることが多いのに対し、敷金は、通常、敷引きがなく、実費精算です。
3. 保証金は、法律上規定のないお金ですが、敷金は、民法第316条、第619条などに規定のあるお金です。
ただし、判例では、敷引きのない保証金は「敷金」と同じ扱いとなっているようです。
ただし、判例では、敷引きのない保証金は「敷金」と同じ扱いとなっているようです。
4. 保証金は、約定がないと権利の承継がありません(次の家主に引き継がれない)が、敷金は原則として新しい家主にも引き継がれます。
5. 保証金=敷金+礼金という解釈もあります。
つまり、保証金方式をとっている場合には、同時に、敷引きなどがある代わりに、礼金を取ることがなく、敷金方式をとっている場合には、敷引きがない代わりに、礼金を取る地域が多いということです。
つまり、保証金方式をとっている場合には、同時に、敷引きなどがある代わりに、礼金を取ることがなく、敷金方式をとっている場合には、敷引きがない代わりに、礼金を取る地域が多いということです。
【法的解説】
法改正により状況がより明確になっています。
敷金の法規定:
旧民法の時代は、敷金に関する直接的な定義規定はなく、判例の積み重ねによってルールが形成されてきました。しかし、2020年4月1日施行の改正民法で、第622条の2として敷金の定義、返還義務、充当に関するルールが明文化されました。これにより、「敷金」の法的性質は極めて明確になりました。
保証金の法的性質と判例の考え方:
保証金には今も法律上の直接規定はありません。しかし、判例が示すように、名称が「保証金」であっても、その契約内容が「債務を担保する目的で預けられ、原則として返還されるべき金銭」である場合、その性質は民法上の「敷金」と実質的に同じであると判断されます。このような場合、民法の敷金に関する規定が類推適用(類似の事柄についてのルールをあてはめること)されることになります。
したがって、「敷引きのない保証金」は、法的にはほぼ「敷金」として扱われます。